ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
水の歴史館 井戸と井戸掘りの変遷 1.井戸の種類 (1)まいまいず井戸
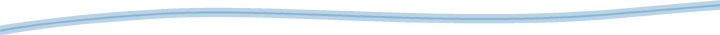

1.井戸の種類
(1)まいまいず井戸
井戸は地面に穴を掘り、その中に地下水を貯めて利用する施設のことをいいます。帯水層(礫や砂からなる透水層で、地下水を含んでいる地層)まで穴を掘れば、自然と水が湧いてくるので、水がある限り半永久的に水を利用することが出来ます。
井戸の種類は大きく分けると、掘井戸と掘抜井戸の2つに分類されます。地方によってさまざまな呼び名がついていますが、基本的な構造は同じです。
帯水層が深いところにあるところでは、「まいまいず井戸」(東京都羽村市)のように直径十数メートルの大きなすり鉢状の穴を掘り、その中心に掘井戸が造られています。その縁には水を汲みに行くための井戸道(いどみち)がつけられています。
すり鉢状に掘り下げられたところにある井戸水を汲みに行くための道が、カタツムリ(でんでん虫)の形に似ていることから、このような名前がついています。この井戸は地元伝説では大同年間(806-810)に創始されたものとしていますが、典拠はなく、形態や板碑(いたび)などの出土から見て、鎌倉時代の創建と推定されています。
井戸掘りの技術の発達していない時代に、垂直の井戸が掘りにくい関東ローム層の砂礫層(されきそう)地帯へ井戸を造るためには、このような形態の井戸が、最も安全で確実な方法だったのではないでしょうか。
※ 「まいまい」とは、多摩地方での「カタツムリ」の方言ですが、なぜ「まいまい」に「ず」がついたのかは不明です。
取材協力:東京都羽村市役所・羽村市郷土博物館
| 【東京都指定文化財】 まいまいず井戸(東京都羽村市)  地表面での直径:約16m 底面の直径:約5m 深さ:約4.3m |
中心にある掘井戸(現在:石積み) 井戸の直径:約1.2m 深さ5.9m 写真提供:東京都三鷹市立井口小学校 |










