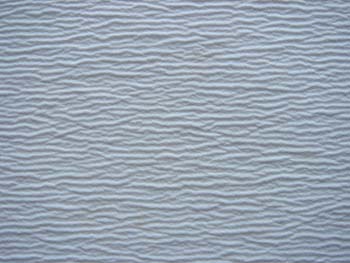本文
水の歴史館 手漉き和紙の出来るまで
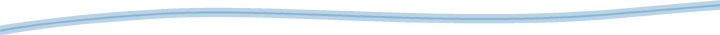

原料
楮(こうぞ)クワ科の落葉低木
 楮の花 写真撮影:青木繁伸(群馬県前橋市) |
本州以西の山野に生え、暖かい南面の山腹傾斜地の風の当たらないところが栽培に適しています。桑の実に似ていて、1年間で2~3メートルほどの高さになります。 葉の長さは5~15センチほどで柄があって互生し、広卵形で先がとがっています。雄雌同株で4~5月に紫っぽい淡黄緑色の単性花を咲かせ、6月頃にはキイチゴに似た赤い実が熟します。甘味があって食べることが出来ます。 樹皮は和紙の原料に使われます。また栽培が容易で収量も多く、1~2月頃の冬眠期間に毎年収穫することが出来ます。 繊維は太くて長く強靭なので、障子紙、表具用紙、美術紙、奉書紙、その他幅広い用途に使われています。 |
 楮の実 写真撮影:青木繁伸(群馬県前橋市) |
|
 刈り取られた楮(右)と三椏(左) |
三椏(みつまた)ジンチョウゲ科の落葉低木
 自然の三椏 西条市大保木 |
中国中南部やヒマラヤ地方が原産で本州関東以西の四国・九州などで主に植栽されています。日本には室町時代に渡来したようです。 和紙の原料(皮)として知られています。7月頃に新しい枝の先端が3本に別れて伸びるので、「ミツマタ」と呼ばれるようになりました。 日本では暖地に栽培され、高さは約1~2メートルほどになり、苗を植えてから3年毎(2月中旬~下旬の開花前)に収穫をします。 三椏は全体が柔らかく、「やなぎ」とも呼ばれています。 葉は楕円形で互い違いの向きに生え、花は初秋から樹木の先につぼみをつけます。2月下旬~4月上旬頃に黄金色の可憐な花を咲かせ、かすかな芳香を放ちます。 身近なものでは紙幣の原料としても広く知られています。 平地ではほとんど見られませんが、石鎚登山ロープウェイで下谷駅(しもだにえき)から少し上がったところに、3月中旬~4月初旬頃、ひっそりと黄色い花が咲いています。石鎚登山の時にゴンドラから下をちょっと覗いてみてください。「黄色い花が私です」。 |
 かわいい三椏の花 西条市大保木 |
|
 石鎚登山ロープウェイ(下りの場合左側斜面) |
蒸し
蒸し
|
|
平釜の底に水を入れて、高めの底板を敷きます。 刈り取った三椏を一定の長さに切りそろえたものを、釜の中に入れます。 楮の場合は、約1メートルぐらいの長さに切り揃えます。 |
|
|
上から「甑(こしき)・がわ」をかぶせ、下から薪を焚いて2時間ほど蒸します。 中の芯が膨張して、切り口から飛び出したようになっていたら蒸し上がりです。 |
皮剥ぎ
楮の皮剥ぎ
 楮の皮剥ぎ作業 |
釜から一束づつ楮を出して、熱いうちに楮皮を手早く剥いでいきます。 根元の楮皮を握り、グイッ!とひとひねりすると芯と皮が分離します。 割れた楮皮を右手でつまみ、左手で芯を握り、左右に開くと簡単に皮を剥ぐことができます。 楮を蒸すと、サツマイモや、豆を炊いたときと同じような臭いがたちこめます。 |
黒皮の乾燥
 剥ぎだちの楮皮 |
楮の皮剥ぎで出来た黒皮を、縛ったところが乾くまで竿に吊るして自然乾燥させます。 |
表皮削り(ヘグり)
 自然乾燥中の黒皮 |
乾燥した黒皮を水に2~3時間浸しておき、柔らかくなったら、「ヘグり台」の上へ皮を上側にして広げ、包丁で押さえ、皮を引っ張って黒皮・甘皮をヘグり、白皮(しろかわ)にします。 ヘギ(そぎ)落とされた黒皮・甘皮は、晒して再利用するため、無駄なものはひとつも出ません。 |
白皮
 |
表皮削りの済んだ白皮を乾燥させ、原料として保存しておきます。 和紙作りには黒皮・白皮共に使われますが、白皮のほうが白いきれいな紙が出来ます。 現在は、原料の楮は地元でほとんど取れないため、土佐楮やタイ楮などを使っています。 |
原料の煮熟(にじゅく)
白皮の煮熟
 |
苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)、ソーダ灰(炭酸ナトリウム)、消石灰などを加え、繊維を柔らかくしていますが、草木灰(そうもくばい=草木を焼いて出来た灰)が好ましいといわれています。 白皮の楮3束13貫(約50kg)をまとめて釜にいれ、4~5時間煮熟します。楮が均等に炊けるように、1時間に一度叉木(またぎ)で釜の中の天地をひっくり返します。 煮熟後は、一晩釜の中で寝かせます。(一晩寝かせておいた方が漂白効果が高いといわれています) 一晩経ったら煮汁を抜いて(捨てて)、1束を水槽に移し、漂白作業へ進みます。 |
 |
晒し(さらし)
 |
2日くらい真水に晒(さら)し、苛性ソーダ、ソーダ灰、消石灰などの煮汁を抜きます。 その後、食器洗用洗剤を入れ、1~2日間真水ですすぎます。 |
漂白
 |
漂白剤で漂白をします。 洗剤を流した後は、漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム=通称:カルキ)で漂白を行います。夏場では1日間、冬場では2日間ぐらい漂白をし、そのあとで塵(ちり)取りを行います 。 |
叩解(こうかい)
叩解作業(昔) 楮打ち
 |
漂白した白皮(しろかわ)の繊維の塊(かたまり)を、桜やビワの木の「打ち台」に乗せ、「打棒」(うちぼう=樫やビワ製)で1時間くらい叩いて紙料にします。 今では、この道具はほとんど使われませんが、「張り」「艶」「しなやかさ」のある紙を作るには、この方法が一番だといわれています。 |
叩解作業(今) 機械打ち
 ホレンダービーター(ステンレス製) |
現在はホレンダービーター(オランダで1670年に発明)で漂白した楮を砕いて繊維をほぐしています。 国安や石田では、このことを「紙料をさぶる」といいます。 水槽の中を、紙料(原料)が叩かれながら、反時計方向にグルグルと回り、徐々に細かく砕かれていきます。右側がホレンダービーター、左側奥が洗浄機です。 叩解の度合いは、紙の出来栄えに大きく影響するため、あげはん(原料を仕上げる人)が度々バケツや杓(しゃく)で掬(すく)い取り、水を混ぜて叩解具合を確かめます。 奉書紙・壇紙の運転時間は約1時間ぐらい、画仙紙の場合は麦藁(むぎわら)が入るため、約2時間ぐらいかかります。 |
 叩解具合を確認しているところ |
紙料
|
|
叩解の終わった原料は、ホレンダービーター下部の水槽に溜め、水分を取り除いたら紙料になります。 |
紙料とタズ(粘液)の調合
糊空木(ノリウツギ) ユキノシタ科の落葉低木
 雨に濡れた糊空木の花(石鎚山) |
高山に自生し、高さは2~5メートル程になります。 アジサイに似た可憐な白い花を咲かせます。 樹皮などから採取した粘液を和紙を漉くときに用いたことからこの名前が付けられたようです。 国安や石田では、北海道産の糊空木(北海道ではサビタと呼ばれている)が使われています。 石鎚山(1,982m)や寒風山(1,763m)で7月中旬から8月中旬頃に花を観賞することが出来ます。 |
 糊空木の生皮を加工して保存したもの |
タズ
|
|
木綿のタズ袋でろ過した液体を漉槽(すきふね)に入れて攪拌します。 糊空木から取れた粘液を東予地方ではタズと呼んでいますが、越前地方ではネリと呼んでいます タズは、水の粘度を高くすることで、漉槽の中で繊維の沈降や絡み合いを防ぎ、簀(す、すだれ)から水が落ちるのを抑えてくれます。 タズは、流し漉きのときの簀の上で、繊維の分散操作を行う時間を“紙漉きさん”に与えてくれています。 |
|
|
紙料とタズの調合
 熊手で紙料とタズを混ぜ合わせる |
水を張った漉槽に、「叩解した紙料」をほぐしながら入れ、「混ぜ板」や「攪拌棒」でかき混ぜます。さらに「熊手」を前後に激しく揺らしてかき混ぜます。続いてタズを入れ、再度、「熊手」でかき混ぜて漉槽の紙料濃度を均等にして紙料液を作ります。 |
熊手の構造
|
|
熊手は左右で構造が違っています。竹製で三角柱の形に作られており、爪の向きは真ん中から正反対に取り付けられています。 紙料とタズが漉槽内で回りながら混ざるようにするための工夫です。 |
|
|
抄紙(紙をすくこと)
流し漉き
 汲み込み 汲み込み写真:山本屋 |
流し漉きでは、化粧水を浅く汲み込んだ後、「簀渡し」(すわたし)を行い、素早く広げ、繊維の薄い膜を作ります。 次は、最初よりやや深く汲み、前後左右に体全体を使ってリズミカルに動揺させ繊維を絡ませます。また汲み込みを行い、前後左右に動揺させて紙料を躍らせます。必要な厚さになるまで、この操作を数回繰り返します。 素人の目から見ると、いつ前後左右に揺ったのか分からないので、まるで神業のようです。 仕上げには化粧水を汲み込み、「捨て水」を行い漉き上げます。 いろんな条件下でも、常に一定の厚さに漉き上げるのが“匠”の技というものなのです。 |
 簀渡し 写真:杉野博美製紙所 |
寒漉きの紙が一番
 調子 写真:マルショウ製紙所 |
古くから、「紙は寒漉きの紙が一番!」といわれています。 寒漉きの紙がなぜいいかというと、温度が低いとタズに包まれた繊維が分散しやすくなり、紙の繊維が絡みやすくなるから良い紙が出来るのです。 また、タズは多糖類の一種で、分子は鎖のように長い形をしていますが、温度が低いと、分子の鎖が結合しやすくなります。 ちょうど水温が4℃の時に水の密度がいちばん大きくなるため、紙漉きには最適の温度といわれています。これに対し、温度が高くなると、水の密度も 小さくなり、タズの分子も鎖が切れて短くなるため、繊維の分散効果が悪くなります。 |
 捨て水 |
弓と吊りひも
 弓と吊りひも |
天井にある弓(真竹の棒)の反動を利用して紙漉きを行います。 弓と吊りヒモは簀桁の微妙なバランスをとるために必要なものです。 紙漉きをしている最中は弓が生きているかのように“しなり”、見ているだけでも楽しい光景です。 吊りひもは、多少弾力のある丈夫な手綯い(てない)の棕櫚(しゅろ)ヒモを使います。 |
紙床(しと)
 |
漉きあがった紙は、簀桁から簀を外し、「漉詰板」(すきづめいた=紙床の置き台)の上に、湿紙を気泡が出ないように注意しながら重ねていきます。 簀は手前から降ろした後、手前から引き上げます。次は反対の面を下にして、次の紙を漉いていきます。 |
圧搾(脱水)
自然圧搾
 |
紙床の上に押掛板(おしかけいた)を置き、均等に圧をかけたまま一晩寝かせます。 この作業をしないと、次のプレス機にかける作業の際に、紙がグチャグチャになってしまいます。 |
機械圧搾
 |
プレス機で徐々に圧搾(あっさく)して水分を抜いていきます。 |
再湿
 |
時々水をかけて水分を補充しておきます。湿らせ過ぎても紙がグチャグチャになってしまうため、ほど良い湿らせ具合が大切です。 ※水分を抜いた紙をまた湿らせる理由。
|
乾燥
天日乾燥(栃板)
 天日乾燥(栃板) |
一枚一枚「紙つけ刷毛」で干し板(栃の木)に貼りつけ、天日で乾燥させます。冬なら半日ほど、夏なら1時間ほどで干し上がります。 今でも封筒を作る時など、特に木目が欲しいときなどには、干し板に貼り付けて天日乾燥をしています。 |
天日乾燥(トタン板)
 天日乾燥(トタン板復元) |
戦後から昭和50年(1975)頃まではトタン板で天日乾燥をしていた時期がありました。 亜鉛メッキ処理をしたトタン板は軽くて熱効率も良く、紙は乾きやすいですが、古くなると錆が出るのが欠点でした。 |
加熱乾燥(その1) 回転式 三角型湯乾燥機
|
|
現在は、ほとんどの製紙業者がステンレス製の湯乾燥機〔川之江の篠原朔太郎が明治40年(1907)に発明〕を使っています。 湿紙を一枚づつ剥がして、ステンレスの板の上に乗せ、紙つけ刷毛で気泡を抜きながら貼り付けます。 天候に左右されず、2~3分で乾燥できるため、効率がよく、安定した生産が出来ます。 しかし、工程の違いからくる紙のしなやかさでは、自然乾燥にはかないません。 |
|
|
加熱乾燥(その2) 回転式 六角型湯乾燥機
 |
冬場の作業は、ホッカ!ホッカ!と暖かく、快適に作業をすることが出来ます。 しかし、夏場の作業は、滝のように流れ出る汗をふき取りながらの作業になるため、大変な重労働です。 |
加熱乾燥(その3) 立体型大型湯乾燥機
 |
大型紙の乾燥に使われます。 この作業は、背丈の高い人に向いています。 |
検品
検品(目視検査)
 |
破れ・損傷・汚れやムラがないかを、また、紙の良し悪しや厚さを一枚一枚選別します。 |
断裁
手裁ち(てだち)
 画仙紙を手裁ちしているところ 写真:森田猛製紙所 |
乾燥した紙の上に大きな板の定規(板の周りの枠は樫製)を乗せ、「紙裁ち包丁」で四方を断裁し、続いて規格の寸法に断裁します。 昔は、全て手裁ちで断裁が行われていました。和紙の全盛期には、石田地区で2人、国安地区で7、8人程度、紙裁ちだけを業とする紙裁ち職人さんがいたそうです。 現在、東予地区で手裁ち(てだち)の出来る“紙漉きさん”は石田地区の森田さんただひとりです。 |
紙裁ち包丁
 画仙紙を切るための紙断ち包丁(石田) |
石田の「紙断ち包丁」は鍛冶屋さんで作ってもらいますが、全て同じに焼入れされたものはありません。人間にも和紙にも個性があるように、包丁にも個性があるのです。 最初、左上のような形ですが、何年も使い込んだ包丁は右下のような形になります。 紙裁ち包丁は普通の包丁に比べると厚みが薄く出来ています。また、石田地区の包丁には柄が付いていませんが、国安地区の包丁(土佐より購入)には柄が付いています。 また、紙の切り方にも違いがあって、石田地区は返し切り(往復切り)をしますが、国安地区では片側からの一方切りです。 それは、画仙紙(硬い)と奉書紙(柔らかい)の紙の硬さの違いによるものだと考えられます。 |
 奉書紙や檀紙断裁用の紙断ち包丁(国安) |
機械裁ち
|
|
現在の断裁作業は、ほとんどが機械裁ちで行われています。ここにもコンピュータ化の波が押し寄せています。 |
檀紙が出来るまでの工程
床取り→紙つけ→シボ寄せ→乾燥
床取り
|
|
湿紙の左下の角を“紙つけはん”(上をつける人)が器用な手でつまみ上げ、1枚づつ丁寧に剥がし、付け台に乗せていきます。 越前は上から紙を剥がしますが、国安・石田では下から剥がします。 |
紙つけ
|
|
“紙つけはん”が付け台(栃の木製)の上に、3枚になるまで湿紙を貼り付けていきます。 |
シボ寄せ(しわ寄せ)
 |
やや斜めに置いた付け台の上端に桟(さん=薄い三角形の板)を敷いておき、まず、付け台の上に1枚の紙を置き、紙つけ刷毛で貼り付けます。
その上端に2枚目の桟を置いて、2枚目の紙を置き、紙つけ刷毛で丁寧に貼り付けます。3枚目も同じように貼り付けます。 次に2枚の桟と3枚の紙を両手でつまみ、手前に一定の角度を付けて、素早く剥がします。 すると、「ちりめんシボ」(しわ)の凹凸(おうとつ)の付いたきれいな壇紙が出来上がります。 上の2枚は完成品で、一番下の紙は、次の工程の2枚目以降の紙として使います。 いい紙が生まれるかどうかは、愛媛県伝統工芸士の“匠”の腕の見せどころです。 |
 紅花染め檀紙 写真:マルショウ製紙所 |
|
 紅花入り檀紙 |
乾燥(室内自然乾燥)
|
|
檀紙の乾燥作業は特殊で、出来上がったシボの付いた湿紙は、シボを保つため、天井の玉掛けに吊るして、自然乾燥をします。 この仕掛けは、国安の松木薫氏(現在101歳)が昭和30年頃、京都の印刷屋の印刷物の干し場を見学させてもらい、それを参考に自分で玉掛け(ラムネの玉止め)の器具を製作しました。使ってみたところ非常に便利で、国安・石田へと広まっていきました。 |
檀紙のシボ
|
|
檀紙とは奉書を厚く漉いた上品な紙にシボ寄せしたものをいいます。 檀紙は、和紙の中では特に格調高い紙といわれ、皇室行事や、格調高い祝儀用品などに使われています。 現在では、ディナーマット、ポチ袋、箸包み、コースターなど広い用途に使われています。 |
ドウサ加工(にじみ止め加工)
ドウサ引き
|
|
表面処理をする方法の代表的なものが「ドウサ引き」といわれるものです。 膠(にかわ)を煮た物の中にロジン(生成した松ヤニ)と明礬(みょうばん)を混ぜ合わせた液を、長刷毛で丁寧に一枚一枚塗って、にじみ止め加工をすることです。 この処理をした紙はほとんど滲みが止まり、書道用紙や日本画の用紙として使われています。 |
乾燥(屋内自然乾燥)
|
|
ドウサ引きの済んだ和紙を両手で持って、人指し指の甲でビー玉を跳ね上げ、すばやく玉掛けに紙を差し込んで吊るしていきます。 室内で乾燥を行うため、人見戸(ひとみど)の間隔の調整をしながら、風の流通を図っています。 また、気候や、その日の天気などにも気を配らなければ良い和紙にはなりません。 |
紙つけ刷毛
|
|
シュロ刷毛(左端) |
国安での檀紙づくりの始まり
国安檀紙の創始者
|
|
国安では、昭和27年(1952)までは主に奉書紙が生産されており、檀紙は生産されていませんでした。 昭和27年頃、松木薫と取引のあった大阪の紙問屋から「檀紙を作ってみてはどうか」という話が持ちかけられました。 当時、檀紙は越前(現在の福井県北部の今立町近辺)が本場。その製造技術はいまだに門外不出で、秘密のベールに包まれたままです。 当時、檀紙は現金取引きで、大変魅力のあるものでした。そこで松木薫は、持ち前の旺盛(おうせい)な好奇心と器用さを活かし、檀紙製造の研究に没頭していました。 ところが、昭和28年(1953)、運命の日が何の前触れもなくやってきました。 たまたま“フシ”(漉き始めと漉き仕舞いに漉く厚めの紙のこと)を数枚重ねて剥いだとき(剥げたとき)、繊維がちぢれているのに気付き、試行錯誤を繰り返しながら、昭和28年、ついに檀紙の製造方法を開発しました。 松木薫が開発した檀紙の製造方法は、門外不出とし、檀紙を作り続けていましたが、昭和35年(1957)頃には他の同業者も檀紙を作り始めるようになりました。 その後も檀紙を作り続けていましたが、昭和45年(1970)の台風10号で作業場が大きな被害を受けたため、それを機に廃業しています。 今でも国安では、当時の製造技術がそのまま引き継がれ、檀紙がつくられています。 |
|
|
|
|
|
(写真・資料提供)東予手すき和紙振興会・西条市立東予郷土館