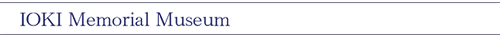本文
五百亀記念館-五百亀について

| 五百亀記念館Top | 五百亀について | 五百亀の作品紹介 |
| 施設案内(ご利用について) | 催物・教室 | 休館カレンダー |
| 五百亀記念館だより |
彫刻家伊藤五百亀(いとういおき) 人生を極める道
愛媛県新居郡大保木村黒瀬(現西条市黒瀬)に生まれた五百亀は、彫刻好きの父親の影響を受け彫刻と出会う。この頃、雑誌『キング』で紹介されていた彫刻家の帝展出展作品を見て、その美しさに感動したことから、彫刻家になることを決心した。当時の決意のことについて後年「雑誌の彫刻を見ましてね、よし、これ位なら自分でもやれるのではないかと思ったんです。父親をどうにか説得して上京したわけですよ。本当に彫刻が好きだったんですな。」と語った。
昭和15年、多摩帝国美術学校(現在の多摩美術大学)中途退学。その後、吉田三郎に師事。本格的な制作活動に入った。
昭和17年、第5回文部省美術展覧会(文展)で《立像》が初入選。翌年の第6回文展には《鍬の戦士》を出品し特選を受賞。
昭和47年、«潮先»を西条市民センター(当時)に建立する。この作品は五百亀36歳の時、第10回日展に出品され、2回目の特選を受賞した作品であり、若々しさ、たくましさ、未来性などを青年の姿によって表現したものである。寄贈にあたり五百亀は「潮先というのは、これから潮が満ちてくるということでたいへんめでたい意味がある。私が戦時中、一時仕事をやめていて、再出発の起点にするために制作した思い出深い作品だ。西条市もいまから未来が開けてくるようにとの願いを込めてこの作品をつくった」と語った。この«潮先»は現在も西条市役所本庁に設置され、西条市の未来を見つめている。
その後も写実性の中に理想の人間像を追求し、昭和49年、56歳で«うたかたの譜»文部大臣賞、昭和57年には«渚»で日本芸術院賞を受賞する。
五百亀は、作家としての心の内面を重視することに重きを持ち続け、「無心になることが何よりも大切である」とその厳しさを語っている。五百亀にとってそれは普段の生活でも変わらず、自らのことを「忍耐強い亀が五百も集まっているから」と本名に結び付け謙虚に語りつつ、自らを極める彫刻家として貫き、多くの秀作を世に残した。
伊藤五百亀略歴
|  |
〒793-0023 愛媛県西条市明屋敷238番地2
Tel・Fax:0897-53-1008
E-Mail:iokikinenkan@saijo-city.jp